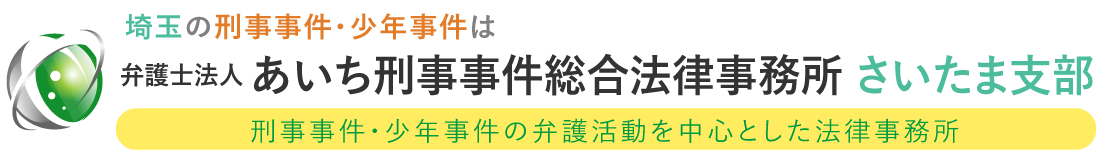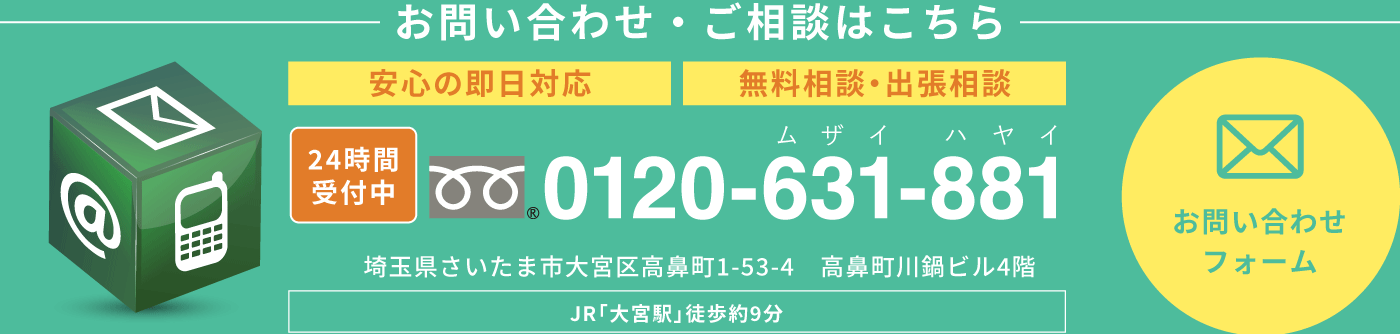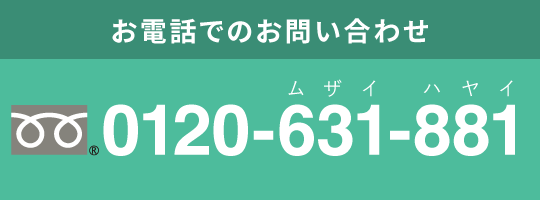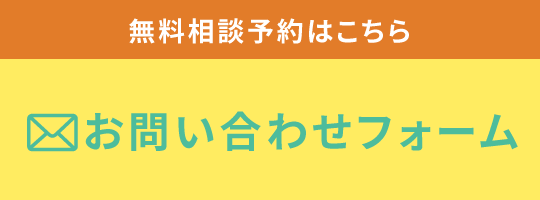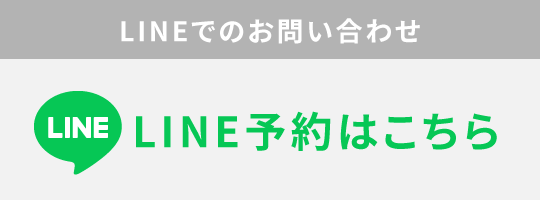Author Archive
【報道解説】電車内の痴漢で逮捕
【報道解説】電車内の痴漢で逮捕
東京都で電車内での痴漢の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「電車内で20代の女性の体を触ったとして、警視庁が東京都迷惑防止条例違反の疑いで、同庁亀有署交通課に所属する30代の警部補の男を現行犯逮捕していたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。
逮捕容疑は1日午後11時40分ごろ、東京都世田谷区を走行中の小田急線の電車内で女性の尻を触ったとしている。
捜査関係者によると、同僚と酒を飲んだ後だった。近くにいた女性の知人が気付いて取り押さえ、駅に駆け付けた警察官に引き渡した。既に釈放されているという。」
(令和4年4月4日に産経新聞より引用)
【痴漢事件で無罪を主張したい場合】
紹介した報道のように電車内での痴漢事件は、防犯カメラの映像などの客観的証拠が無いことが多く、痴漢をやっていないと刑事裁判で争う場合は、痴漢事件を疑われて起訴された被告人の供述や、被害に遭われた被害者の方や痴漢事件の目撃者の供述内容を検討して、どの供述が信用できるのか、どの供述が信用できないのかという形で争われることが多いです。
【痴漢事件で無罪となった裁判例】
電車内の痴漢事件において、被害者の供述が信用できるかが問題になった裁判例のひとつに千葉地方裁判所平成27年1月14日判決があります。
この裁判例では、足の踏み場の無いほど混雑した電車内で、女性の服の上から左胸を手で揉んだという痴漢事件の犯人が、被害に遭った女性の正面で左向きに立っていた被告人であるのかが問題になりました。
被告人が犯人であると立証するための証拠が被害女性の供述しかなかったことから、裁判所は被害女性の供述に信用性があるかを検討しました。
裁判所は、検討の結果、被害女性の供述は信用性が乏しいと判断しました。
そのような判断の理由として、被害女性の犯人が被告人であると判断した供述についてはその判断過程に飛躍があったこと、痴漢行為時の被告人の体勢に関する供述が被害女性の憶測に基づいてなされた可能性があること、犯行内容に関わる重要な事実について被害女性が一貫した供述をしていないかった等の点を挙げることが出来ます。
他方で、裁判所は、被告人の供述は逮捕当初から一貫して犯行を否認しており、供述内容にも特に不自然・不合理な点はないと裁判所は判断しました。
以上を踏まえて、裁判所は、犯人が被告人であるということを証明することができないため、被告人は無罪であるという判決を下しました。
このように、供述の信用性が問題になる場合には、供述内容自体に不自然・不合理な点がないか、供述が捜査過程から一貫しているか、争いのない事実や客観的証拠によって立証される事実と供述内容を比較した際に、両者に整合性があるかという点が信用性判断のポイントになるでしょう。
【刑事事件の解決のために】
やってもいない痴漢を疑われて警察の捜査を受けてお困りの方は、刑事弁護の経験が豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士から取調べなどの警察の捜査に関してアドバイスを貰うことで、捜査過程において一貫した供述をしておくことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、痴漢の否認事件をはじめとした刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
痴漢冤罪でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道紹介】風俗店の経営者を装って準強制性交等罪で逮捕
【報道紹介】風俗店の経営者を装って準強制性交等罪で逮捕
京都府で準強制性交等罪の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【報道紹介】
「京都府警中京署は令和4年4月14日、準強制性交の疑いで、京都市右京区のコンビニアルバイト店員の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は同年3月22日午後9~10時ごろ、中京区のビジネスホテルで、自分がデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の経営者であるように装い、採用のために必要な勤務の講習と信じさせ、大阪市の無職女性(46)を乱暴した疑い。
中京署によると、男は同日に女性と交流サイト(SNS)で知り合ったという。」
(令和4年4月14日に京都新聞より引用)
【解説】
13歳以上の者に対して暴行・脅迫を用いたうえで性交・口腔性交・肛門性交(この3つをまとめて「性交等」といいます)を行った場合は、刑法177条が規定する強制性交等罪が成立します。
今回報道でとり上げた事件では、準強制性交等罪の疑いで逮捕されたとあります。
この準強制性交等罪は、刑法178条2項に定められている犯罪で、強制性交等罪とは異なり、暴行・脅迫を用いずに性交等を行った場合に成立し得る犯罪になります。
具体的には、準強制性交等罪は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした」(刑法178条2項)場合に成立します。
「心神喪失」とは、失神・熟睡・泥酔・高度の精神障害などによって、自分に対して性交等が行われることの認識がない状態をいいます。
「抗拒不能」とは、自分に対して性交等がなされる認識はあるものの、物理的・心理的に抵抗できない場合をいいます。
報道では、逮捕された方が風俗店の経営者であると装って、被害者の方に対して乱暴をしたとあります。
被害に遭われた方からすれば、勤務を希望する風俗店の経営者と称する人から、これからの勤務の際に必要な講習であると性交を求められた際には、これを断って不採用となる事態を回避するために、性交を受け入れざるを得ない心理的状況であったのでしょう。
このように、風俗店勤務希望の人に対して風俗店の経営者であると騙って、心理的に性交を断ることができなくなる状況を作ったことが、「抗拒不能」にさせたとして、準強制性交等罪の疑いで逮捕された可能性があります。
なお、準強制性交等罪が成立すると、5年以上の有期懲役の刑が科せられることになります。
【刑事事件の解決のために】
準強制性交等罪を犯してしまった場合の刑事弁護活動として、被害者の方との示談交渉が非常に有効です。
弁護士を通じて、被害者の方に誠心誠意謝罪の意思を示して、許してもらうことが出来れば、検察官による起訴を回避する可能性を得られます。
準強制性交等事件でお困りの方は、まずは刑事事件に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、準強制性交等事件などの風俗に関連する事件についての弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
風俗関連のトラブルで警察沙汰になってしまった方や、ご家族の方が準強制性交等罪の疑いで逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】裸の自撮り動画と不正アプリで個人情報を抜き取り恐喝
【報道解説】裸の自撮り動画と不正アプリで個人情報を抜き取り恐喝
京都府でSNS上で性的な自撮り動画を入手した上で、不正アプリをダウンロードさせて個人情報を抜き取り、更に金銭を要求するという恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「京都府警によると、府内に住む10歳代の男性は令和3年8月、出会い系サイトで知り合った女性に求められ、自身の下半身が映った動画をSNSで送った。
女性から『私のも見たかったらこれを入手して』と促され、指示されたアプリをインストールすると、文面が急変。『(男性の)動画を親族や友達に送りつける。嫌なら金を払え』とのメッセージが送られてきたという。女性側に伝えていないのに、男性がスマホの電話帳に登録する親族の電話番号も示されていた。」
「男性が府警に相談し、金銭的被害はなかったが、動画の回収はできないままだ。府警は、個人情報を抜き取る不正アプリが使われたとみている。」
「こうした不正アプリはネット上で多数確認されており、情報セキュリティー会社「トレンドマイクロ」(東京)によると、不正アプリをインストールすると、遠隔操作などで電話番号やメールアドレスなどを抜き取られてしまうという。」
「不正アプリの送信者に対して、警察当局は不正指令電磁的記録供用罪の疑いなどで摘発している。」
(令和4年4月13日の読売新聞より引用)
【罰則の解説】
上記報道の被疑事実に関連して、同様の事案で成立する可能性がある犯罪としては、児童ポルノ法違反、青少年健全育成条例違反、不正指令電磁的記録供用罪、恐喝罪が考えられます。
1.児童ポルノ法違反の可能性
まずは、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反の可能性についてです。
報道では10代の男性が、出会い系アプリで知り合った女性の求めに応じて、下半身の自撮り動画を送ったとの記載があります。
仮に、下半身の自撮り動画を送った男性が18歳未満であれば、その動画を受け取った者は、児童ポルノ禁止法違反になり、刑罰が科される可能性があります。
具体的には、自分の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持・保管は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります(児童ポルノ禁止法7条1項)。
また、第三者に提供する目的で児童ポルノを所持・保管していた場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童ポルノ禁止法7条3項・2項)が、不特定又は多数の者に対して提供する目的で児童ポルノを所持・保管していた場合は、罪が重くなって、5年以下の懲役若しくは500万円の罰金が科せられ、又はこれらを併科されることになります(児童ポルノ禁止法7条7項・6項)。
2.各都道府県の青少年保護育成条例違反の可能性
なお、18歳未満の者に対して下半身の自撮り動画を要求はしたが、送ってもらえなかった場合には、青少年保護育成条例違反に問われる可能性がある自治体があります。
例えば、東京都では、東京都青少年健全育成条例の第18条の7に違反することになり、30万円以下の罰金となります(同条例第26条7号)。
3.不正指令電磁的記録供用罪の可能性
報道では、男性が動画を送った相手方の女性の裸を見たいがために、女性の指示に応じて女性が指定した不正アプリをダウンロードしたとあります。
この不正アプリをダウンロードさせる行為は、不正指令電磁的記録供用罪に当たる可能性があります。
不正指令電磁的記録供用罪は、正当な理由なく、コンピューターウイルスなどの「電磁的記録」を、他人のスマホやパソコンといった「電子計算機」のなかで、「実行の用に供する」場合に成立する犯罪です(刑法168条の2第2項)。
「実行の用に供する」とは、スマホやパソコンの使用者の意思とは無関係に、コンピューターウィルスを実行される状態に置くことを言います。
そのため、正式なアプリを装って、ウィルスが組み込まれている不正アプリをインストールさせる行為は「実行の用に供する」場合に当たることになるでしょう。
この不正指令電磁的記録供用罪が成立すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
4.恐喝罪の成立可能性
続けて報道では、ダウンロードさせた不正アプリによって、男性のスマホから家族や友人の連絡先などの情報を抜き取った上で、下半身の動画を家族などに拡散されたくなければ金銭を支払えと要求したとの記載があります。
このような脅迫によって実際に金銭を受け取ると、恐喝罪(刑法249条1項)が成立することになるでしょう。
恐喝罪が成立すると、10年以下の懲役となります。
なお、恐喝罪は未遂でも処罰することになっていますので(刑法250条)、報道のように、被害者が金銭を支払う前に警察に相談したため、実際には金銭を支払わずに済んだような場合でも、脅迫をした側は処罰の対象になります。
【刑事事件の解決のために】
引用元の報道では「性行為や裸の画像をネット上で公表されたり、他人に送られたりしたとする相談は、昨年1628件あり、5年連続で過去最多を更新した。」とあります。
そのため、警察はこうした被害を防ぐために、積極的に捜査に乗り出している可能性があります。
SNSで繋がった児童から裸の画像等を入手した方、個人情報を抜き取るウィルスを相手方に送ってしまった方、裸の画像を拡散すると恐喝をした方などは、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】ストーカー規制法違反で逮捕
【報道解説】ストーカー規制法違反で逮捕
ストーカー規制法違反で刑事事件化した場合における刑事手続と刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【事例紹介】
「令和4年4月7日、兵庫県警伊丹署は同僚女性(46)の携帯電話に行動を監視しているようなメッセージを送ったとして、伊丹市交通局職員の男(60)を、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕した。」
「発表によると、男は同年4月5から7日、無料通信アプリ「LINE」で、仕事中の同僚女性を撮影した写真とともに「俺は見ているぞ」などのメッセージを送った疑い。令和3年1月頃からメッセージが増え始め、多い日には昼夜を問わず50件届いたという。」
(令和4年4月8日に読売新聞より配信されたニュースより引用)
【ストーカー規制法で逮捕されるケースとは】
ストーカー規制法では、大きく「ストーカー行為」をしたことにより逮捕されるケースと、「禁止命令等」に違反したことにより逮捕されるケースがあると考えられます。
まず、「ストーカー行為」に当たる場合についてですが、「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、「つきまとい等」の行為を反復してすることを言います(2条4項)。
なお、「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知りうる状態に置くこと」(2条1項2号)や「拒まれたにもかかわらず、連続して、電子メールの送信等をする」(2条1項5号)といった一定の場合には、「ストーカー行為」が成立するためには「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に」という限定が付きます
それでは、どのような行為が「つきまとい等」に当たるのでしょうか。
ストーカー規制法では「つきまとい等」に当たる行為として大きく8つの行為を定めていますが、ここでは、冒頭でとりあげたニュースの内容に関わる限りで「つきまとい等」について説明します。
ニュースでは、3月5日から7日にかけて、同僚女性に対して、仕事中に撮影した女性の写真と一緒にLINEで「俺は見ているぞ」などのメッセージを送り、このようなメッセージを昨年1月ごろから、多い日には昼夜を問わず50件送ったとの記載があります。
ストーカー規制法では、「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置く」行為(2条1項2号)を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」で行った場合には、「つきまとい等」に当たるとしています。
「俺は見ているぞ」というメッセージは、監視していると告げる行為そのものですから、2条1項2号によって「つきまとい等」に当たることになるでしょう。
そして、同僚の女性に対して仕事中の女性の姿を撮影した写真と一緒に「俺は見ているぞ」というメッセージを多い日には昼夜を問わず50件もLINEで送った場合、そのようなメッセージを受け取った側からすれば、「自分は常に監視されている」と思い、「いつか何かされるのではないか」「家に突然押し掛けるのではないか」などど「身体の安全」や「住居等の平穏」が害されるような不安を感じたり、あるいは、「自分が行く場所が全て把握されているのはないか」と「行動の自由」が著しく害される不安を覚えさせるような「つきまとい等」として、「ストーカー行為」に当たる可能性が十分にあります。
「ストーカー行為」をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります(18条)。
【刑事事件の解決のために】
今回は、ニュースの内容に沿って、監視していると告げる行為によってストーカー規制法違反になり得る場合について説明しました。
監視していると告げるメッセージでなくても、LINEでしつこく「会いたい」「忘れられない」などのメッセージを送った場合にも、「つきまとい等」に当たる場合があります(2条2項1号、2条1項5号)。
また、昨年令和3年にはストーカー規制法が改正され、相手方の承諾を得ないでGPS機器などを用いて位置情報を取得する行為や、相手方の所持する物にGPS機器などを装着する行為などについては、「位置情報無承諾取得等」として新しく規制の対象になりました(2条3項)。
「位置情報無承諾取得等」を同一の者に対して反復して行った場合には「ストーカー行為」に当たることになりますし、一定の場合には「禁止命令等」が出され、これに違反すると罰則が科されることになります。
このようにストーカー規制法違反といっても様々な場合があり得ます。
そのため、警察からご家族の方をストーカー規制法違反で逮捕されたという連絡があった場合、まずは弁護士にご相談して、現状を把握されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、ストーカー規制法違反をはじめとした刑事事件の弁護経験が在籍しております。
ご家族の方がストーカー規制法違反で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【解決事例】覚醒剤取締法違反の逮捕事案で不起訴処分獲得
【解決事例】覚醒剤取締法違反の逮捕事案で不起訴処分獲得
成人男性による覚醒剤取締法違反被疑事件の刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が紹介します。
【被疑事実】
本件は、男性被疑者Aが、自動車運転で事故を起こした際、鞄の中に覚醒剤が入っていたことが捜査機関に発覚したため、覚醒剤所持の疑いで逮捕されたという覚醒剤取締法違反(覚醒剤所持)の事例です。
Aは覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された後、事件が検察官送致され、検察官が勾留請求し、裁判官が勾留を認めたため、Aは覚醒剤取締法違反の疑いで勾留された後で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護の依頼がありました。
覚醒剤所持の疑いによる勾留期間中に捜査機関によるAの尿検査が進行し、Aの尿から覚醒剤使用の痕跡が認められたため、Aは覚醒剤所持の疑いによる勾留については処分保留で釈放となりましたが、同日づけで、覚醒剤使用の疑いで逮捕(再逮捕)され、この後、覚醒剤使用の疑いで勾留が決定しました。
【刑事弁護の経緯 終局処分に向けて】
本件では、弁護士契約の締結時点でAが勾留されていましたが、覚醒剤取締法違反などの薬物犯罪では勾留の不服申し立て(準抗告)の難易度が高いことや、今回の覚醒剤所持および使用の疑いの背景について被疑者が否認しており、その主張を尊重するため、勾留の取消を目的とした身柄解放活動ではなく、検察官が本事件を起訴するか否かを決める終局処分に向けて弁護活動に注力していきました。
Aの主張としては、Aが自動車事故で負傷し意識が朦朧としていた中で、捜査機関がAの無許可に乗じてAの鞄を漁って覚醒剤を発見した可能性がありました。
これは刑事手続上、令状の無い状況下での違法な強制捜査に該当する可能性があり、このような違法な捜査中に収集された証拠については、その証拠能力が否定される可能性があったため、弁護士はその方向性での弁護活動を進め、Aが捜査機関の取り調べに対して、Aの認識とは異なる事実を調書に記録されないよう、黙秘するよう指導を続けました。
結果として、覚醒剤使用による覚醒剤取締法違反の疑いによる勾留期間の満了時、検察官は本刑事事件を起訴しない(不起訴処分)とする決定を下しました。
【依頼者からの評価】
本刑事事件のような覚醒剤の所持および使用に関する覚醒剤取締法違反の薬物犯罪では、被疑者は逮捕に引き続いて勾留が下され、その後検察官が起訴して公開の刑事裁判となることが実務上の通例です。
しかし、検察官は具体的な理由は回答しませんでしたが、本件について検察官が不起訴処分としたからには、有罪に足る十分な証拠が収集できなかったと推察することが妥当と考えられます。
AおよびA両親には、本刑事事件が無事に不起訴処分で終わってことについて、大きな感謝の言葉をいただきました。
【刑事事件の解決のために】
前述のとおり、覚醒剤取締法違反などの薬物犯罪の刑事事件は、被疑者段階で勾留を阻止したり、勾留を取消すことは非常に難しいため、基本的には被疑者に不当な取調べがされたり、事実とは異なる事実を自白させられることがないよう、取調べ対応を十分にケアしたうえで、起訴後の公判に備えていくことが重要となります。
薬物犯罪のような通常起訴されることが予想され、公開の刑事裁判となる可能性が高い刑事事件について、執行猶予つき判決など少しでも軽い処分を目指したい方は、刑事事件を専門とする多数の刑事裁判の経験のある弁護士に弁護を依頼することが望ましいでしょう。
覚醒剤取締法違反で刑事事件化してお悩みの方、またはご家族が逮捕されてお悩みの方は、覚醒剤取締法違反を含む薬物犯罪の刑事裁判の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】児童福祉法違反の性犯罪で逮捕
【報道解説】児童福祉法違反の性犯罪で逮捕
児童福祉法違反の疑いで被疑者が逮捕された報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道】
逮捕されたのは、岐阜県海津市の26歳の看護師の男で、令和4年1月から2月にかけて、複数回にわたり勤務する岐阜県内の病院に入院していた18歳未満の少女にわいせつな行為をさせた児童福祉法違反の疑いが持たれています。
令和4年2月8日、少女が岐阜県警が設置する性犯罪被害の相談窓口に「入院中に男性看護師に体を触られた」と相談をしたことで事件が発覚しました。
(令和4年3月25日に配信された東海テレビより引用)。
【解説~児童福祉法~】
この報道の中では「児童福祉法」に違反したとして、被疑者が逮捕されました。
児童福祉法は、児童の心身の健全な育成のために定められた法律で、児童の福祉のために認められる権利や支援、施設に関する規定があります。
こうした児童福祉法では、罰則をもって禁止されている行為があり、その中のひとつが、児童福祉法34条1項6号になります。
児童福祉法34条1項6号では、18歳未満の「児童に淫行をさせる行為」を禁止し、これに違反すると、児童福祉法第60条1項により、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科した刑が科されることになります。
【解説~淫行とは~】
児童福祉法の「児童に淫行をさせる行為」については、平成28年6月21日に出された重要な最高裁判所の判例がありますので、今回はこの判例について簡単に説明します。
この判例は、「淫行」の意味と、「させる行為」に当たるか否かの判断のための要素を呈示しています。
まず、「淫行」の意味ついては、「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」のことをいうと判断しています。
これは、性交や性交に準ずる性交類似行為の中で、さらに、児童の健全な育成を阻害するおそれがあるものに限定することを意味します。
こうした解釈からは、真摯な交際関係の下で行われた性行為は「淫行」に当たらないことになる可能性が高いですが、他方、単に自身の性欲のはけ口にするためだけに児童と性行為をするような場合は、「淫行」に当たることになります。
そして、「させる行為」の意味については、「児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいう」と述べた後で、「させる行為」にあたるか否かの判断は、「行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断する」と述べました。
そして、この判例では、被告人が16歳の被害者の方が通う高校の常勤講師であり、高校内で性的接触を持った後で、ほどなくホテルで性交したという事実関係のもとで、被告人が被害者の方と性交をした行為を「淫行をさせる行為」であると判断しました。
今回取り上げた報道において、仮に「淫行」行為の事実が認められた場合、「させる行為」があったか否かの判断については、この判例に従ってなされることになるでしょう。
報道によると、逮捕された看護師の方と被害に遭われた児童の方との間には、看護師の方が児童の治療を担当していたという関係があったとのことですので、この関係の影響がどれほどのものであったかがひとつのポイントになりそうです。
【刑事事件の解決のために】
今回は、看護師の方が児童福祉法違反の疑いで逮捕された報道を取り上げました。
報道のように、ご家族の中で、児童福祉法違反の疑いで逮捕されてしまった方がいる場合、いち早く、刑事事件に精通した弁護士に依頼して初回接見に向かってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、弁護士から今後の事件の見通しや今後の対応について適切な助言を貰うことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童福祉法違反を始めとした刑事弁護の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の方が児童福祉法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【解決事例】器物損壊罪の在宅事案で示談成立と不起訴処分獲得
【解決事例】器物損壊罪の在宅事案で示談成立と不起訴処分獲得
成人男性による器物損壊被疑事件の刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が紹介します。
【被疑事実】
本件は、男性被疑者Aが、パチンコ店Vの店前に置いてあったティッシュケースに対して火のついたタバコを投げ捨てた結果、ティッシュケースを焼損したという器物損壊罪の事例です。
Aは器物損壊罪の疑いで逮捕されましたが、検察官が勾留請求せずAを釈放したため、以後は在宅捜査へ切り替わりました。
Aは釈放後、器物損壊罪で今後どのような刑事手続を受け、どのような刑事処罰が下るのか不安となり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部で弁護士契約いただく運びとなりました。
【刑事弁護の経緯 終局処分に向けて】
本件では、Aが逮捕後に釈放されて以後は在宅捜査となったため、次の段階として、被害者であるVに対する示談交渉を進めました。
Aは、タバコの投げ捨てによる器物損壊の被疑事実を認めており、Aが謝罪と賠償の意向があるとVに対して連絡をとり、数度の交渉を経て、無事に示談を成立させることができました。
示談内容として、Vが器物損壊罪の刑事告訴を取り下げてもらう条項も入っていたため、本件器物損壊罪はVの刑事告訴の取下げにより起訴の要件を満たさなくなったため、検察官は本事件を不起訴処分と決定しました。
【依頼者からの評価】
本刑事事件は、刑事事件化から不起訴処分の決定まで、約1カ月ほどで解決に導くことができました。
器物損壊罪は被害者からの刑事告訴がなければ検察官が起訴することができない「親告罪」であるため、比較的円滑かつ早期に示談が成立したため、不起訴処分獲得までスピード解決をすることができました。
Aはとにかく前科をつけたくないとの念で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に弁護士契約をいただいたため、事件が無事に不起訴処分で終わってAは大変安心していらっしゃいました。
【刑事事件の解決のために】
上記刑事事件のように、器物損壊罪などの親告罪の刑事事件は、何よりも示談の成立によって被害者から刑事告訴を取り下げていただくことが刑事弁護の最重要課題です。
このような親告罪の刑事事件で不起訴処分を目指したい方は、刑事事件を専門とする多数の示談経験のある弁護士に弁護を依頼することが望ましいでしょう。
器物損壊罪で刑事事件化してお悩みの方、またはご家族が逮捕されてお悩みの方は、器物損壊事件の示談成立と不起訴処分獲得に実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
少年の性犯罪と少年法改正の影響
少年の性犯罪と少年法改正の影響
少年による強制性交等罪などの性犯罪事件を取り上げ、令和4年4月1日から施行される改正少年法との関連で今後変化する少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
【刑事事件例】
埼玉県さいたま市大宮区在住の高校3年生Aさん(18歳)は、同じ学校の女子Vさんと交際をしていましたが、Vさんから別れを切り出されたことに不満を感じていました。
その後、AさんがVさんに対して復縁を迫った際に激しい口論となり、その結果、AさんはVさんに強いて性行為を行いました。
後日、Vさん両親から埼玉県警大宮警察署に対して強制性交等罪の被害が訴えられ、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕され、10日間の勾留が決定しました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どれぐらい長く勾留され、今年4月の民法改正による成人年齢が18歳に引き下げられる中、Aさんがどのような法律上の責任を負うことになるのか不安になり、刑事事件と少年事件に詳しい弁護士に相談をすることにしました。
(上記刑事事件例はフィクションです。)
【少年法改正】
令和3年5月21日に少年法改正法案が成立し、今年令和4年4月1日から施行されます。
この少年法改正は、同日づけの成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正とセットになって、今後の刑事事件および少年事件に大きな影響を与えることになります。
今回の少年法改正は、従来よりも重い法律上の責任を与える民法改正と足並みをそろえるべく、罪を犯した18歳、19歳の者を「特定少年」と位置づけ、17歳以下の少年とは異なる法的手続きが行われることになります。
少年法上の「少年」とは20歳未満の者であり、この点に少年法の改正はありません。
ですので、「特定少年」についても、少年法改正後も少年法が適用されることには変わりありません。
よって、基本的には「特定少年」の少年事件は、原則として全件家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で処分を下されることになります。
ただし、従来から、たとえ少年事件であっても一定の重大事件であれば成年と同じく刑事裁判手続きへ差し戻す「逆送」という規定がありました。
「特定少年」の少年事件では、今回の少年法改正により、逆送の対象となる範囲が従来より拡大されることになり、「死刑、無期懲役または短期1年以上の懲役・禁錮の罪」に該当する事件が逆送範囲に加わるため、例えば、現住建造物等放火罪、強盗罪、強制性交等罪、組織的詐欺罪などの少年事件が原則として逆送され、成年と同じく刑事裁判を経て刑事責任を負うことになります。
また、少年事件は、少年の実名や写真等の報道が原則禁止されているところ、少年法改正によって、特定少年の事件が逆送され、検察官によって起訴されて刑事裁判が決定した場合には、少年の実名や写真等の報道が可能となります。
【少年事件も刑事事件専門の弁護士へお任せ】
少年法改正によって、今後「特定少年」として成年と同じ刑事責任を負うことになる事案が増加することが予想されます。
刑事事件の手続き自体に成年と少年の区別はありませんが、とはいえ少年の精神年齢の未熟さや環境に対する影響の受けやすさを考慮すれば、被疑者または被告人として厳しい責任追及を受ける少年に寄り添って刑事弁護活動を行うことができる弁護士が今後より一層必要とされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門として国内で数少ない法律事務所であり、成年の刑事事件の不起訴獲得や執行猶予獲得はもちろん、少年の不起訴処分獲得や保護観察処分の獲得などで多くの実績をあげ、依頼者様から高く評価をいただいております。
埼玉県さいたま市大宮区で、少年による強制性交等罪などの性犯罪事件で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
万引きのつもりが裁判員裁判に?
万引きのつもりが裁判員裁判に?
万引きで問題となる罪と、それが事後強盗罪、強盗致死傷事件に発展した場合に考えられる裁判員裁判の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説致します。
【ケース】
埼玉県川口市在住のAは、専業主婦として生活をしています。
Aは生活に困っていたわけではありませんが、生活費を少しでも浮かせたいと考え、いつも利用しているスーパーマーケットで日用品を購入する際、商品数点をレジを通さず買い物かごに入れる万引き行為を日常的に行っていました。
被害に遭っていたスーパーマーケットでは私服警備員を配備し、事件当日もAが万引き行為を行った場面を現認しました。
そこで、警備員VはAが店を出たところで「清算していない商品をお持ちですよね」と問いかけました。
Aは怖くなって逃げようとしましたが、警備員VはAの前に立ち尽くしたため、逃げようと思い警備員Vを突き飛ばしました。
警備員Vは弾みで道路に倒れ込み、頭部を激しく打って後遺症がでる重症を負いました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【万引きと事後強盗】
ご案内のとおり、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店舗で陳列棚などから商品を盗む行為は、いわゆる万引きと言われ窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
しかし、今回の事件のように、店員や警備員などから声をかけられ、商品を取り上げられたり通報されそうになったりした場合に、相手に対して暴力行為をしたり脅迫する行為は、事後強盗という罪に当たります。
刑法238条に記載のとおり、事後強盗にあたる行為は強盗罪として扱われます。
ケースについて見てみると、Aの事後強盗事件により警備員Vは道路に頭部を激しく打って後遺症が生じるほどの外傷を負っています。
強盗事件を起こした結果、被害者が死傷してしまった場合、強盗致傷罪・強盗致死罪という罪にあたります。
事後強盗事件の場合も同様に扱われるため、以下で引用している刑法
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
【事後強盗が被害者を怪我させた場合は裁判員裁判の対象に】
裁判員裁判は、以下のいずれかに当たる罪を犯した場合に開かれます。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項各号)
①死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
②法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪(強盗等を除く。))であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件
ケースの場合、つまり強盗致傷罪の場合は、無期懲役刑が用意されているので、裁判員裁判対象事件にあたります。
裁判員裁判対象事件で起訴された場合、司法試験に合格して法曹資格を有する「裁判官」だけでなく、一般人で構成する「裁判員」も審議に参加し、有罪か無罪か、有罪の場合の量刑はどうするか、決めることになります。
裁判員裁判は通常の裁判とは異なる点が少なくありませんが、
・公判前整理手続や裁判員の選任手続きがあるため起訴から判決宣告までに時間がかかる
・裁判官だけでの審議に比べ、市民感覚が反映されより厳しい刑罰が科せられる可能性がある
という特徴が挙げられます。
そのため、集中審議前に保釈請求を行ったり、集中審議では裁判員にもわかりやすいような書類等の作成・説明が求められたりするなどといった、技術や経験が不可欠です。
よって、裁判員裁判対象事件で起訴される可能性がある場合、早期に裁判員裁判の経験がある弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当法人では、これまで数多くの刑事事件を経験していて、裁判員裁判で無罪、あるいは執行猶予を獲得した経験もあります。
埼玉県川口市にて、家族が万引きをしたところ店員や警備員に制止され、突き飛ばすなどして事後強盗事件や更に重い強盗致傷事件に発展した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に御連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
建造物等以外放火で逮捕
建造物等以外放火で逮捕
建造物等以外放火で逮捕された場合における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説いたします。
事例
埼玉県蕨市在住のAは、蕨市内の会社に勤める会社員です。
ある日、蕨市内の駐車場にて、駐車されていたVの自動車に何者かが放火し、周りに駐車されていた他の車3台を含めてこれらを焼損させました。
消防からの通報を受けて臨場した蕨市内を管轄する蕨警察署の警察官は、捜査の結果Aによる放火事件であるとし、建造物等以外放火事件で通常逮捕しました。
なお、Aは上記事実を否認しています。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)
~建造物等以外放火罪~
放火罪はその危険性から重大な犯罪として、(個人のみならず社会の安全を脅かすものとして)位置付けられている犯罪です。
放火罪は、取り返しのつかない重大な被害が生じる危険性が大きいことから法定刑も重い犯罪ですが、その放火の対象によって成立する犯罪や法定刑が大きく異なります。
本件で、放火の対象として問題となっているのは建造物等以外の物です。
(建造物等以外放火)
第110条 放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
「前2条」とは、現住建造物等放火罪(刑法108条)と非現住建造物等放火罪(刑法109条1項・2項のことを指し、本件の放火対象からは外れます。
本件では、Vの自動車という「前2条に規定する物以外の物」が放火の対象となっています。
そして、放火の対象となった自動車は「自己の所有」ともいえないことから、刑法110条1項の他人所有建造物等以外放火罪の成否が問題となるのです。
110条1項においては、108条や109条1項とは異なり、明文で「公共の危険」の発生を犯罪の成立要件としています。
では、「公共の危険」とは、どのような事態を指すのでしょうか。
判例(最決平成15年4月14日)は、「公共の危険」とは、「108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険に限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる」としています。
本件では、Aはマンションの駐車場内でV所有の自動車に放火し、これを含め4台の車を焼損させたとされています。
この事実を前提とすると、上記判例においては「駐車場において、放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだ」ことをもって「公共の危険」の発生を認めていますから、実際に他の3台を焼損させるに至った本件においては「公共の危険」は明らかに認められるといえるでしょう。
~刑事弁護士の役割~
被疑者(容疑者)や被告人の弁護活動というと、世間からは必ずしも理解を得られないことがあります。
よくある世間の方からの疑問は「なぜ悪い奴の味方をするのか」といった類いのものでしょうか。
しかし、犯行のその瞬間を写した鮮明な防犯カメラなどの映像があれば別かもしれませんが、絶対的な真実に到達することはそう容易いことではありません。
多くの事件では、グレーな部分が残るのであり、否認事件に限らず事実関係を含め争いが一切ないケースの方が稀なのではないでしょうか。
特に、本件のような否認事件の場合には、捜査官は被疑者・被告人から不利益な供述を得ようと躍起となる場合も少なくありません。
それは、過去に(そして現在も)捜査機関が違法な捜査等によって冤罪事件を生み出し続けていることからも非現実的な想定とはいえないのです。
そこで、弁護士として、捜査官に対する対応を含め、具体的に分かりやすい対応策を説明することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、放火事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
埼玉県蕨市内にて、ご家族が建造物等以外放火事件で逮捕された場合、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
担当の者が弁護士との無料相談や警察署等への初回接見サービスについて詳しくご案内いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。