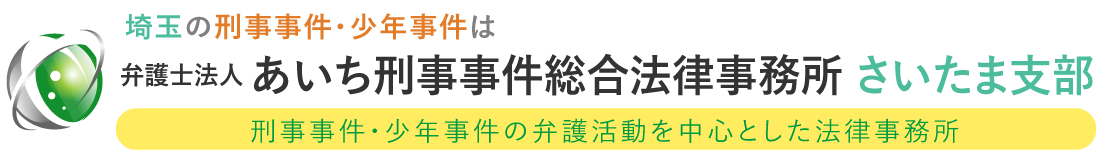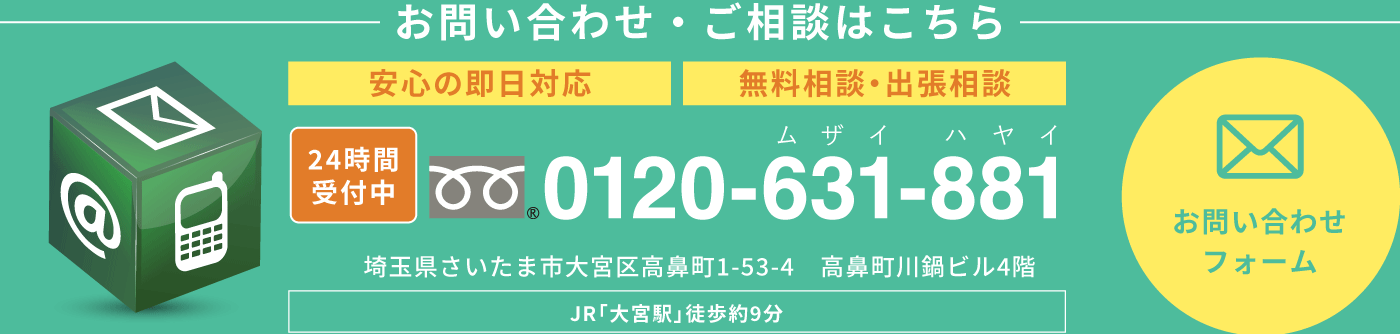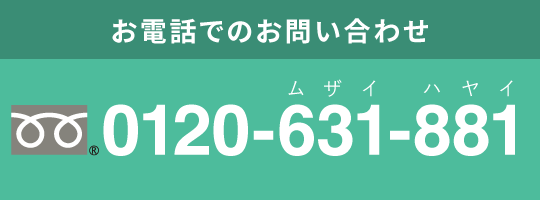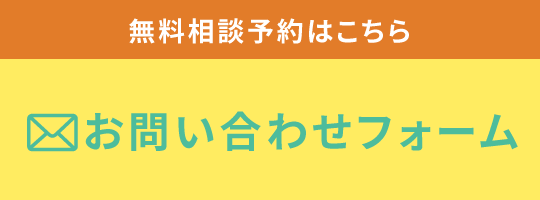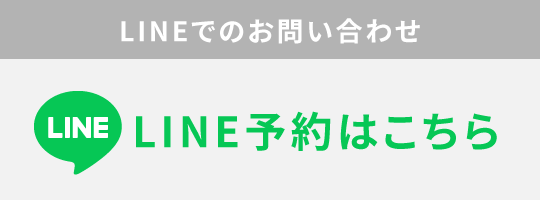Author Archive
【報道解説】埼玉県越谷市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪で逮捕
【報道解説】埼玉県越谷市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪で逮捕
万引き(窃盗罪)などの犯罪が発覚して逃走するために暴力を振るった場合、非常に重大な事後強盗罪へ発展する可能性とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
埼玉県越谷市の質店で、エルメスのハンドバッグ3点を盗んで逃げ、追いかけてきた店員に催涙スプレーを噴射したとして、33歳の女Aが逮捕されました。
A容疑者(33)は5日、午後6時30分ごろ、埼玉県越谷市の質店でエルメスのハンドバッグ3点、約390万円相当を盗んで逃げる際に、追いかけてきた20代の女性店員に催涙スプレーをかけた事後強盗の疑いがもたれています。
警察によりますと、A容疑者は質店から50m逃走したところで、店の外から犯行を目撃していた男性に取り押さえられ警察官に引き渡されました。
A容疑者は取り調べに対し、「バッグが欲しくなって数点とって逃げました。店員さんが追いかけてきたので、催涙スプレーをかけました」と容疑を認めています。
(令和7年7月6日のABEMA TIMESの記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【強盗と事後強盗】
通常、「強盗」とは、暴行または脅迫を用いて他人が反抗することができない状態にさせ、その反抗抑圧中に財物を奪うことを意味します。
強盗における暴行または脅迫は、社会通念上、客観的に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされており、逆に、個々具体的事案における被害者の主観を基準とするものではないとされています(判例)。
上記刑事事件例は、通常の強盗とは異なり、万引き(窃盗)犯が、店員や・警備員・保安員などの追及を逃れるために暴行を加えて財物を奪ったという事案であり、これは刑法第238条の事後強盗に該当します。
具体的には、窃盗を行った者が、財物を得た後で取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、罪跡(証拠)を隠滅するために、暴行又は脅迫を加えた場合、通常の強盗と同じ罪となります(事後強盗、刑法第238条)。
判例によれば、窃盗罪の犯人が、犯行を目的して追跡してきた者による逮捕を免れるために暴行を加えた時、事後強盗罪が成立するとされており、窃盗の既遂後、窃盗現場から1キロほど離れた場所において、窃盗から30分ほど経過した後に、犯人を追いかけてきた被害者に対して、盗品を取り戻されまいと暴行を加えた場合にも、全体から見て、窃盗の機会の延長線上で行われた暴行と言えると判断し、事後強盗罪の成立を認めた判例もあります。
事後強盗罪は強盗罪と同じ扱いなので、法定刑としては5年以上の有期拘禁刑が科されることになります。
【事後強盗罪は重大犯罪】
事後強盗罪の事件で、かつ、上記のように被害者に対して傷害の結果も生じさせたような場合、事実関係によっては強盗致傷罪の扱いがされる可能性があります。
もし強盗致傷罪と同じ扱いで起訴されると次に示すように通常の公判手続とは異なる点があります。
まず、強盗致傷罪のように法定刑で無期拘禁刑が定められている事件が起訴された場合、その事件は、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判制度は、職業裁判官と一緒に、国民の中から抽選で選ばれた人が裁判員として裁判に参加して、有罪・無罪の判断、有罪の場合の量刑をどうするかを決める裁判制度です。
裁判員裁判制度においては、量刑を判断にあたっては国民感情が反映されることになりますので、職業裁判官のみによって行われる通常の裁判に比べて、量刑が重くなる傾向があると言われています。
また、裁判員裁判の対象となる事件については、公判が開かれる前に公判前整理手続と呼ばれる手続が行われることになります。
公判前整理手続は、第1回公判期日の前に、裁判所、検察官、弁護人が事件の争点を明確にして、証拠の整理を行い、これからどのように審理を進めていくかという審理計画を作成することを目的とする手続ですが、審理計画の作成に時間がかかってしまい、結果として公判が長引いてしまうおそれがあります。
【強盗罪関連の弁護活動】
このように強盗罪関連の刑罰は、法定刑が非常に重く重大な犯罪です。
ただし、被害者に対する示談の有無によって、刑事処罰の可能性を低くする可能性が残されています。
事件を起訴するか否かを決定する権限は検察官にあり、検察官が事件を起訴するか否かの判断をするにあたっては、被害に遭われてしまった方の処罰感情を重視する傾向にあります。
そのため、検察官が起訴不起訴の判断を下すまでに、被害に遭われてしまった方に対して謝罪と被害の回復を行い、示談を締結することができれば、軽い処分となる可能性を高めることができます。
さらに、事後強盗の特徴として、特に店員、警備員や保安員に対する事後強盗のように、財物の所有者という窃盗罪の被害者と、暴行または脅迫を受けた被害者が異なるケースがあります。
当初は強盗罪(事後強盗)の疑いで刑事事件化または逮捕されていた場合でも、例えば暴行被害者に対する示談が成立して、被害届の取下げや刑事処罰を求めない旨の合意を得た場合には、検察官は罪状を窃盗罪に切り替えるケースも見受けられるため、重大犯罪である事後強盗で刑事事件化または逮捕された場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に速やかに弁護活動を開始してもらうことが何よりも大切です。
埼玉県越谷市で万引き(窃盗)から暴行ふるって事後強盗罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【事例解説】埼玉県熊谷市で傷害罪で起訴 示談を目指す弁護活動
【事例解説】埼玉県熊谷市で傷害罪で起訴 示談を目指す弁護活動
埼玉県熊谷市で傷害罪で起訴された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事例紹介】
交際相手の女性を暴行してけがさせたとして、埼玉県警熊谷警察署は11日、住居・職業不詳のA容疑者(59)を傷害容疑で逮捕した。
捜査関係者によると、逮捕容疑は今年2月11から12日、交際相手の女性(54)に暴行を加え、肋骨を折るなどのけがをさせたというもの。
被害者女性は同12日、A容疑者に付き添われて負傷した状態で埼玉県内の病院を訪れたという。
医師には「階段から落ちた」と説明し、診察後に帰宅したが、2日後の14日夕方に埼玉県熊谷市の自宅トイレ内で倒れているところを知人が発見して事件が発覚した。
(令和7年7月11日の記事を参考に、犯行場所や被害内容等の一部事実を変更したフィクションです)
【傷害罪とは】
傷害罪(刑法第204条)は他人の身体に傷害を与えた場合に成立します。
ここで言う「傷害」とは、外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪の法定刑においてこのような幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度等が非常に多種多様であることが想定されるためであると考えられています。
例えば、軽い負傷の場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的な暴力行為の場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)が適用され、より重い罰則が科されることとなります。
【傷害罪と示談】
示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。
示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して慰謝料や治療費などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。
示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。
そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。
ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。
刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
【傷害罪で示談を希望するなら】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された場合や、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】埼玉県さいたま市で児童買春逮捕事件
【報道解説】埼玉県さいたま市で児童買春逮捕事件
児童に対する児童買春で逮捕された場合の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
インド国籍の自称カウンセラーの男性(28歳)が、昨年に、当時17歳の女子高校生について、仲介者の男に現金を渡して児童買春をした疑いや、当時14歳と15歳の女子中学生が16歳未満と知りながら、仲介者の男に現金を渡して、2人にそれぞれわいせつな行為をした、不同意性交等罪と児童買春罪の疑いで、埼玉県大宮警察署で逮捕された。
男性は昨年7月に、仲介者の男に現金1万1000円を支払って、さいたま市内のインターネットカフェで同市に住む当時17歳の女子高校生について、児童買春をした疑いがもたれている。
大宮警察署によると、男性は、今年2月に逮捕された仲介者の男の捜査の中で関与が浮上した。
(令和7年6月17日に配信された「関西テレビ」を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【児童買春罪の刑事処罰とは】
児童買春とは、18歳未満の児童に対して、報酬を与えて、あるいは報酬の約束をして、わいせつ行為や性行為等をすることをいいます。
児童買春行為をした場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春禁止法)による刑事処罰の対象となります。
・児童買春禁止法 第4条
「児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」
児童買春罪の刑事処罰の法定刑は、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、児童買春の周旋や勧誘を行った者は「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又は併科」となり、児童買春の周旋や勧誘を業として行った者は「7年以下の拘禁刑及び1000万円以下の罰金」となります。
児童買春逮捕事件では、まずは逮捕から72時間以内の早期釈放を目指すことが重要となります。
弁護士の側より、被疑者が容疑を認めており、これ以上の身柄拘束が必要でない事情や、被疑者の家族が、釈放後の被疑者を管理監督できる環境が整っている事情、再犯のおそれが無い事情などを主張して、早期釈放を働きかける弁護活動が考えられます。
また、警察取調べにおいて、被疑者が事件当日や事件までのやり取りの状況を、どのように供述するかの対応を弁護士とともに検討し、弁護士が、被害者児童の保護者と示談交渉をすることで、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることが、刑事処罰の軽減のための重要な弁護活動となります。
【児童に対する他の性犯罪とは】
児童買春罪が要件を満たさず成立しないようなケースでも、18歳未満の児童に対する他の性犯罪が成立する可能性があることに、注意が必要です。
18歳未満の児童に対して、報酬を渡すことなく、わいせつ行為や性行為をした場合は、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」などに違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
18歳未満の未成年者を、自宅に泊めたような場合には、刑法の「未成年者略取誘拐罪」や「わいせつ目的略取誘拐罪」が成立する可能性も考えられます。
16歳未満の児童に対するわいせつ行為や性行為をした場合には、わいせつ行為や性行為に対して同意できる年齢に達していないとして、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に問われる可能性が考えられます。
まずは、児童買春逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県さいたま市の児童買春逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】埼玉県熊谷市でSNSなりすましによる不同意性交等事件で逮捕
【報道解説】埼玉県熊谷市でSNSなりすましによる不同意性交等事件で逮捕
埼玉県熊谷市でSNSなりすましによる不同意性交等事件に対する不起訴処分に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
SNSで17歳の少女になりすまし、小学6年生の女子児童を自宅に連れ込んで性的暴行を加えた不同意性交等罪の疑いで、埼玉県熊谷市在住の男性(23歳、飲食店従業員)が、埼玉県熊谷警察署で逮捕された。
熊谷警察署によると、男性は昨年10月に、埼玉県熊谷市の自宅で、当時小学6年生だった女子児童に性的暴行を加えた疑いがもたれている。
男性はインスタグラムで17歳の少女になりすまし、接触してきた女子児童に「ゲームをしよう」と誘って自宅に呼び寄せ、犯行に及んでいた。
女子児童が自宅を訪ねてきた際、男性は、なりすましていた17歳の少女の兄を名乗っていたとのこと。
熊谷警察署の取調べに対して、男性は「同意はあった」と容疑を一部否認しているとのこと。
(令和7年6月12日に配信された「TBS NEWS DIG」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【不同意性交等事件の刑事処罰とは】
16歳未満の児童に対して、わいせつ行為や性行為をした場合には、原則として、児童側にわいせつ行為や性行為に対する同意があったとしても、その同意が認められる年齢に達していないとして、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に当たり、刑事処罰を受けます。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」とされており、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」とされています。
・刑法 第177条3項(不同意性交等)
「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」
【不起訴処分に向けた弁護活動の重要性】
刑事事件の捜査の流れとして、警察署に任意出頭しての取調べや、逮捕後の取調べが何度か続いた後に、事件書類や証拠等が検察庁に送られて、検察官が事件の起訴・不起訴の判断を行います。
不起訴処分を得るためには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前の警察取調べ段階、すなわち捜査の初期段階において、弁護士による取調べ供述対応のアドバイスや、示談交渉の働きかけなどの弁護活動を開始している必要があります。
被疑者が逮捕・勾留されている身柄拘束事件であれば、勾留期間(原則10日間、最長20日間)が終わった時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされるため、逮捕直後から弁護士の初回接見(面会)を依頼して、不起訴処分の獲得に向けた取り組みを、前もって進めておくことが重要です。
不起訴処分には、大きく分けて「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。
冤罪主張が認められて、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」による不起訴処分を勝ち取るためには、担当の検察官に対して、被疑者は犯人ではない事情や、他に真犯人がいる事情などを納得させる必要があります。
弁護士の側から、「被疑者にアリバイがあること」「被疑者が犯人であるという目撃者や関係者の供述が嘘であること」「他の真犯人の存在」などといった事情を、客観的な証拠とともに提示し、検察官を説得する方向での弁護活動が考えられます。
他方で、「起訴猶予」による不起訴処分を勝ち取るためには、被害者側との示談交渉を弁護士が仲介する形で進めていき、謝罪や慰謝料支払いの意思を示すことにより、加害者を許す旨を含む示談を成立させることが重要となります。
まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県熊谷市の不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】埼玉県さいたま市で名誉毀損罪で逮捕 示談を目指ざすなら弁護士に相談を
【報道解説】埼玉県さいたま市で名誉毀損罪で逮捕 示談を目指ざすなら弁護士に相談を
埼玉県さいたま市で名誉毀損罪で逮捕された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
昨年12月から今年1月、X(旧ツイッター)上で、県議員V氏の家族の写真とともに「人殺し」などとV氏の名誉を傷つける投稿をしたとして、埼玉県警捜査1課は11日、名誉毀損の疑いで、さいたま市の無職A容疑者(61)を逮捕した。
Aは「逮捕事実の内容を投稿した可能性はあります」と供述しているという。
警察によると、1つのアカウントから複数の投稿を行っていたとみられ、「V君のお父さんは人殺し、殺人鬼です」などとも投稿されていた。
今年2月に県外の成人男性から通報があり事案が発覚。
V氏はその後、被害届と告訴状を提出している。
現在、アカウントは削除されている。
(令和7年6月11日づけ「産経新聞」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです)
【名誉毀損とは】
刑法第230条(名誉毀損罪)によれば、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損」する行為を処罰しています。
名誉棄損罪における名誉毀損の表現とその内容については、適示された内容が「その事実の有無にかかわらず」成立するとしています。
なお、名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金刑とされています。
名誉毀損罪が成立するためには、その事実適示が「公然と」行われなければなりません。
「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態を言いますが、判例によれば、「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しないとされています。
【名誉毀損罪と示談】
示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。
示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して精神的苦痛を与えたことによる慰謝料や、社会的名誉を回復するために必要な対応に必要な金額などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。
示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。
そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。
ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。
刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
【傷害罪で示談を希望するなら】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、名誉毀損罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
名誉毀損罪などで捜査を受けることになり、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】さいたま市浦和区のホテルで児童買春の不同意性交等事件で逮捕
【報道解説】さいたま市浦和区のホテルで児童買春の不同意性交等事件で逮捕
さいたま市浦和区のホテルにおける児童買春による不同意性交等事件を例に、私選弁護人と国選弁護人の性質について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
埼玉県警浦和警察署は、令和6月10日に、13歳の少女にみだらな行為をしたとして、不同意性交罪と児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで、さいたま市在住の医師の男性(37歳)を逮捕した。
男性は「女の子が16歳未満だとは知らなかった」と否認している。
逮捕容疑は1月28日、さいたま市浦和区のホテルで、少女に2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。
浦和警察署によると、2人はインターネットで知り合ったという。
(令和7年6月10日に配信された「共同通信」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【児童買春罪と不同意性交等罪の刑事処罰】
18歳未満の児童に対して、対価として報酬を渡して、わいせつ行為や性行為をした場合には、児童買春罪に当たるとして、「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
他方で、原則として16歳未満の児童に対して性行為をした場合には、児童側が性行為の同意ができる年齢に達していないということで、刑法の不同意性交等罪に当たり、「5年以上の有期拘禁刑」という法定刑で、刑事処罰を受けるおそれがあります。
【私選弁護人と国選弁護人の違い】
私選弁護人とは、犯罪の容疑をかけられた被疑者本人が弁護士を選んで、自身の刑事事件の弁護を依頼する場合の弁護人をいいます。
私選弁護人は、事件が警察に発覚する前の初期段階から、刑事弁護活動を依頼することが可能であり、私選弁護人が早期に事件証拠等の事件状況を分析し、後の刑事裁判に向けた主張・立証に活かすことができます。
国選弁護人とは、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときに限り、裁判所に対して国選弁護人の選任請求をすることにより、選任される場合の弁護人をいいます。
国選弁護人は、「逮捕された事件」や「起訴された事件」において選任できるとされており、「逮捕されていない事件、かつ事件の起訴前の段階」では国選弁護人を選任することはできません。
国選弁護人は、候補リストから無作為に選ばれた弁護士が弁護担当となるため、熱心に全力で弁護活動に当たってくれるかどうかは、その弁護士次第であり、また、あまり刑事事件に精通していない弁護士が事件を担当する可能性も考えられます。
また、「逮捕されていない事件、かつ事件の起訴前の段階」においては、国選弁護人を選任できないため、被疑者本人が私選弁護人を選任して、被害者側との起訴前の示談交渉などを弁護士に依頼することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊かな弁護士による精一杯の弁護活動により、被害者との示談交渉、不起訴処分獲得に向けた働きかけ、勾留阻止による身柄解放などに尽力いたします。
まずは、児童買春の不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
さいたま市の児童買春の不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】会社の金庫から現金窃盗して逮捕 被害弁償・示談の可能性を探る弁護活動
【報道解説】会社の金庫から現金窃盗して逮捕 被害弁償・示談の可能性を探る弁護活動
埼玉県さいたま市で会社のお金を盗んだとして窃盗罪の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
埼玉県さいたま市のスーパーの金庫から現金およそ7500万円を盗んだとして、従業員として働いていた44歳の派遣社員Aが逮捕されました。
警察の調べに対し、「SNS型投資詐欺にはまり、被害金を捻出するために使った」などと容疑を認めているということです。
警察によりますと、去年(2024年)2月までのおよそ3か月間に、30回余りにわたって、さいたま市にあるスーパーの金庫に保管されていた現金あわせておよそ7500万円を盗んだとして、窃盗の疑いが持たれています。
金庫の中の現金が減っているのに店長が気づき、警察に被害届を出したということです。
Aは去年2月にこのスーパーの金庫から現金250万円を盗んだとして、すでに逮捕・起訴されていました。
(令和7年6月9日づけ「滋賀NEWS WEB」の記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【窃盗罪の内容と罰則】
今回取り上げた報道では、会社の現金を盗んだとして被疑者が窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪を定める刑法第235条によれば、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」としています。
窃盗罪は拘禁刑と罰金の選択刑となっており、具体的は犯行内容の悪質性、被害金額の多寡、犯人は前科や犯行回数の程度、犯行に対して酌量すべき情状などによって、幅広く刑罰を科すことができます。
一般的に、犯人に前科がないこと(初犯であること)や、「万引き」に分類される被害額が少ないものに関しては、罰金刑が科されるケースが多い傾向にあります。
しかし、会社内での窃盗など、数多い反復性が想定されるものや、総額としてかなりの被害額に昇ることが多い犯行については、実刑(法改正前の懲役刑)が科されるケースもあります。
【法改正による拘禁刑の導入】
2025年6月1日の刑法改正の施行により、従来の刑罰である「懲役刑」と「禁固刑」が、新しく「拘禁刑」に一本化されました。
これまでの刑罰では、刑務所に収監されている間に、刑務作業の義務がある懲役刑と、刑務作業が任意となる禁固刑に、区別されていました。
拘禁刑では、個々の受刑者に応じて、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、刑務作業を行わせるものとされています。
刑法第12条によれば「拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下」で、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する」ことであり、「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うとができる。」としています。
【勤務先会社に対する窃盗罪が発覚したら】
会社の資金を窃盗したり、着服してしまったなどで窃盗罪等の財産犯罪の疑いが生じた場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
会社内部での窃盗罪については、まず最初に、窃盗の事実に対して会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が窃盗行為に対して刑事告訴を行い、警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多く見受けられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる会社内部の窃盗罪の相談事例についても、まず会社側が窃盗被害の事実を認識し、窃盗行為が疑われている会社員と会社側で話し合いを行い、事実を認め真摯に謝罪して盗んだ現金等を返せば、会社側は刑事処罰については見合わせると申し入れるケースもしばし見受けられます。
そのため、窃盗罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や窃盗金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が窃盗罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。
また、被害を受けた会社側も、少しでも窃盗された金額が返金されることを望むことが多いので、窃盗を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。
このように会社内部での窃盗罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば、前科を付けずに事件を解決することができる可能性があります。
そのような解決を目指すには、窃盗行為が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
埼玉県さいたま市で会社内部での窃盗罪が発覚してお困りの方や、窃盗罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】性的姿態等撮影罪で逮捕 勾留決定前の私選弁護人による早期釈放に向けた弁護活動
【報道解説】性的姿態等撮影罪で逮捕 勾留決定前の私選弁護人による早期釈放に向けた弁護活動
性的姿態等撮影罪で逮捕され、勾留が決定する前の早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
埼玉県警は6月10日、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、埼玉県上尾市在住の会社員の男(46)を逮捕した。
逮捕容疑は、今年3月15日午後3時ごろ、県内の商業施設で、女子小学生に近づいてスカート内にスマートフォンを差し入れ盗撮した疑い。
県警によると、小学生の母親が110番した。
防犯カメラの映像などから犯人の盗撮行為を特定した。
(令和7年6月10日づけ「南日本新聞デジタル」記載の鹿児島県の盗撮事件の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【性的姿態等撮影罪】
令和5年7月13日で、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律が施行され、現在では性的な画像や動画の盗撮行為等は、この法律によって処罰されることが多くなりました。
この法律の第2条を特に「性的姿態等撮影罪」と呼んでいます。
性的姿態等撮影罪では、正当な理由なく密かに性的姿態等を撮影する行為を処罰しています。
性的姿態等とは、例えば、人の性的な部位や、人が身に着けている下着や、わいせつな行為・性交等の姿態を言うとされています。
上記の上記「人の性的な部分」とは、性器・肛こう門・これらの周辺部、臀部・胸部などとされています。
また、上記「下着」についても、特に、通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限るとされています。
さらに、性的姿態等では、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」は除くとされています。
性的姿態等撮影罪については、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科されます。
【逮捕から勾留決定までの流れ】
被疑者が逮捕されると、被疑者は警察官による弁解録取(取調べ)を受け、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、逮捕から48時間以内に事件を検察庁へ送致します。
送致を受けた検察庁では、検察官による弁解録取(取調べ)が行われ、逃亡や罪証隠滅の観点から継続して身柄拘束が必要と判断した場合は、送致から24時間以内に、裁判官に対して勾留請求します。
その後、裁判官が検察官の勾留請求を許可すると、最大10日間(延長されると最大20日間)身柄拘束が続いてしまいます。
そのため、被疑者本人の肉体的・精神的な負担は勿論のこと、長期間会社に行けなくなることによる懲戒解雇等の不利益を受ける可能性が高まります。
【早期釈放のための弁護活動】
早期釈放の観点からは、勾留決定の判断がなされる前に、勾留を阻止するための弁護活動を迅速に開始することが重要です。
なお、国選弁護人制度では、被疑者の勾留が決定した後しか国選弁護人を選任することができないため、勾留前の弁護活動は私選弁護人に依頼する必要があります。
私選弁護人は、検察官や裁判官に対して、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求や勾留決定を行わないよう意見を申述していきます。
具体的には、検察官や裁判官が把握していない、弁護人が被疑者本人や家族や関係者から聴取した被疑者に有利な事情などを提示することで、勾留の理由や勾留の必要性がないこと、またはその必要が低いことを的確に主張し、検察官が勾留請求を行わない、又は裁判官が勾留請求を却下する可能性を高めることを狙います。
【弁護士への依頼】
このように、盗撮(性的姿態等撮影罪)で逮捕された場合における、勾留決定前の早期釈放を実現するには、逮捕後直ちに適切な弁護活動を開始することが極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、盗撮事件での弁護活動により、勾留決定前の早期釈放を実現した実績が多数あります。
ご家族が盗撮事件で逮捕され不安を抱える方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】埼玉県久喜市で運転ミスの人身事故で過失運転致傷罪
【報道解説】埼玉県久喜市で運転ミスの人身事故で過失運転致傷罪
自動車運転中のミスによって人身事故を起こしてしまった場合に生じうる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
6月5日午後、埼玉県久喜市で高齢女性が車にはねられ死亡する事故があり、運転していた92歳の男が現行犯逮捕されました。
警察などによりますと5日午後2時前、久喜市久喜駅近くで「車と歩行者の交通事故」と通行人から119番通報がありました。
久喜市在住のVさん(74)が普通乗用車にはねられたもので、Vさんは病院に運ばれました。
警察は、車を運転していた自称自営業のA容疑者(92)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aは「近くの店で買い物を終えて帰宅途中、車のスピードが出て事故を起こした」などと話しています。
(令和7年6月5日づけ「九州朝日放送」の記事を参考に、事件場所や被害状況等の一部事実を変更したフィクションです。)
【過失運転致傷罪の傾向】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部には、自動車運転上の過失によって人を負傷させてしまった等の交通事故に関する刑事事件の相談が数多く寄せられます。
過失運転致傷罪の刑事事件の場合、現行犯逮捕された場合以外であれば、事実が捜査機関に発覚したからといってすぐに逮捕される訳ではなく、警察から任意の事情聴取を求められ、出頭日をすり合わせたうえで捜査協力を求められることが多いです。
そのため、この時点では、警察においてどのような事情聴取を求められるのか、それに対してどのように答えるべきか等について最も関心がある方が多く、中には自分が厳しい尋問を受けて自白させられ、逮捕されてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。
【過失運転致傷に対する弁護活動】
過失運転致傷罪の被疑事実について心当たりがあるにせよ無いにせよ、この段階では、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自分の認識や記憶にある限り正しい事実を弁護士に伝え、その中で事実をきちんと認め、捜査機関に対して適切な応答ができるよう助言を受けることが大切です。
なぜなら、加害者(被疑者)の認識や記憶にある事実と、被害者や目撃者の認識や記憶にある事実が食い違うことは往々にしてることで、加害者が少しでも自分の責任となることがないよう事実を過小に申告することもあれば、被害者が加害者に対して多くの法的責任を負わせたいがために過剰に事実を申告することもあり、その事実を、刑事事件の経験に長けた客観的な第三者である刑事弁護士に判断してもらい、その中で最も適切な捜査対応を探っていくことが極めて重要となるからです。
例えば、自分の自動車が被害者と接触したことが記憶にないと主張した場合であっても、事実、被害者が負傷をしている以上、その被害者の負傷の原因となった事実の究明に捜査機関は全力を上げることが予想され、特に公道での防犯カメラや目撃者の証言から、被疑者の認識よりも不利な証拠が出てくることも考えられます。
特に、被疑事実をすべて否認するのか、あるいはどの範囲まで否認するのかについては、今後被害者に対して示談を申し出る余地を残すためにも、刑事事件弁護士の客観的な意見を聞いておくことが重要です。
【過失運転致傷の量刑の傾向】
自動車運転死傷処罰法によれば、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が科されます。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。
一般的な傾向としては、重篤な傷害が生じていなかったり、過失の程度が悪質でなければ、50万円程度またはそれ以下の罰金が科される事例が多く見受けられます。
ただし、重篤な傷害が生じていたり、過失の程度が悪質な場合、検察官の公判請求(起訴)によって公開の刑事裁判となり、実刑が争われることが予想され、違法性が高い過失運転致傷罪の例では実刑判決も下されています。
【過失運転致傷で軽い処罰を得るには】
逆に、過失運転致傷罪で、被害者への謝罪や賠償金(または謝罪金等の名目)の支払いがなされており、被害者の被害感情が回復されているような事例では、この点を考慮して検察官が不起訴処分を下すこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部でも、被害者様への謝罪や自動車保険に上乗せとしての謝罪金・賠償金のお支払いの合意にいたり、結果として不起訴処分を獲得した事例が多数ございます。
埼玉県久喜市で、運転ミスで過失運転致傷罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。
【報道解説】埼玉県蕨市で女子生徒盗撮の児童ポルノ製造事件で略式罰金刑
【報道解説】埼玉県蕨市で女子生徒盗撮の児童ポルノ製造事件で略式罰金刑
埼玉県蕨市で女子生徒盗撮による児童ポルノ製造事件の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【報道紹介】
埼玉県教育委員会は、令和7年5月2日に、埼玉県蕨市立中学校の校内で女子生徒のスカート内をスマートフォンで盗撮したなどとして、昨年9月付けで、40代の男性教諭を懲戒免職にしたと発表した。
埼玉県教育委員会は、被害者のプライバシー保護のため発表を遅らせたとしている。
男性教諭は、昨年9月25日に、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕された。
埼玉県教育委員会によると、既に略式起訴され、罰金の略式命令を受けている。
昨年7月に、いすに座っていた学校関係者のスカート内を盗撮していたことが目撃情報で明らかになり、埼玉県教育委員会が聴取した結果、同年5月に女子生徒を盗撮したことも認めたという。
(令和7年5月2日に配信された「共同通信」を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【盗撮による児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】
ひそかに、他人の性的な部位等を盗撮した場合には、性的姿態撮影処罰法違反の「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「性的姿態等撮影罪」の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
また、18歳未満の児童を対象として、ひそかに盗撮行為をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
「児童ポルノ製造罪」の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
【示談交渉による刑事処罰軽減の刑事弁護】
盗撮による児童ポルノ製造事件を起こした場合に、被害者やその保護者との間で示談が成立して、被害者への被害弁償が済んでいる事情や、被害者側の許しを得ている事情があれば、それらの事情は児童ポルノ製造事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響は、さまざまです。
示談成立の際に、「被害者による許しの意思表示」「被害届の取下げの意思表示」「告訴の取下げの意思表示」などがあるかどうかの事情は、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事処罰の量刑が決定される際に、大きく考慮されると考えられます。
しかし、児童ポルノ製造事件を起こした本人が、被害者側と直接の示談交渉を行うことは、被害者感情として加害者を怖がることが危惧されるため、難しいケースが多いです。
そこで、弁護士が間に入って被害者側との示談交渉を進めることにより、不起訴処分獲得や刑事処罰軽減が期待される内容の示談成立に向けて、弁護士が事件解決へと尽力いたします。
まずは、児童ポルノ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県蕨市の児童ポルノ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本で数少ない刑事事件・少年事件を全国規模で取り扱う弁護士事務所であり、当法律事務所さいたま支部は、大宮駅近くに事務所を構え、さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護経験が豊富な弁護士が、初回の法律相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスを受け付けております。弁護士のスケジュール次第では、電話口で事情をお伺いしてから直ちに相談・接見サービスを提供することも可能です。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
ご不明な点やお悩みがある方は、ぜひお早めにご相談ください。