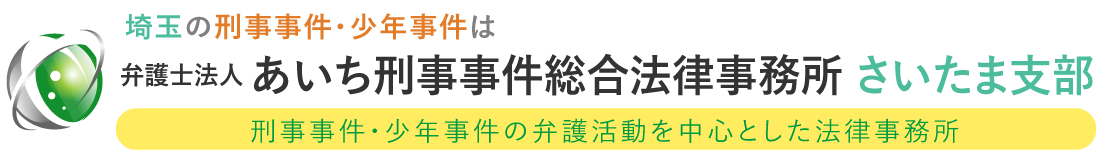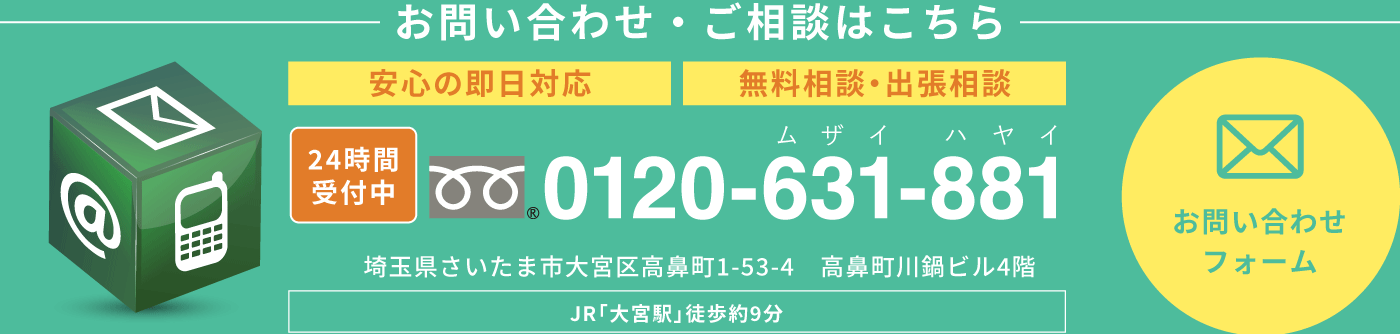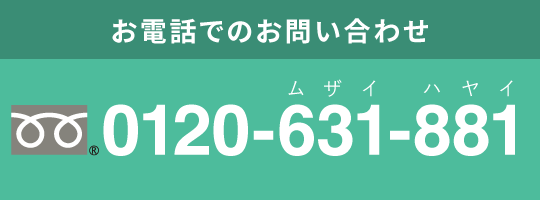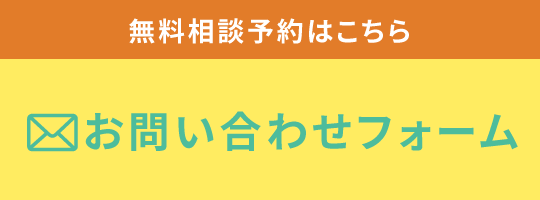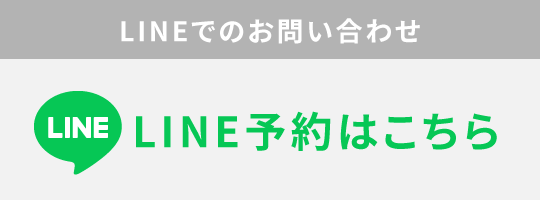※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
大麻関連の法改正
近年、特に若年層で、大麻の乱用の拡大が顕著になってきており、より厳しい規制が必要となってきました。
一方で、国際的に大麻の医療上の有用性が認められ、大麻草の医療や産業でのより有効な活用の需要も高まってきました。
そこで、「大麻草の医療や産業における適正な利用を図るとともに、その乱用による保健衛生上の危害の発生を防止するため、①大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とするための規定の整備、②大麻等の施用罪の適用等にかかる規定の整備、③大麻草の栽培に関する規制の見直しに係る規定の整備等の措置を講ずる。」趣旨で、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立しました。
改正の概要
大麻の施用(使用)の処罰
令和6年12月12日より、大麻は「麻薬及び向精神薬取締法」の「麻薬」として規定されることになりました(同法第2条第1項第1号の2)。これにより、コカイン等他の麻薬と同様に施用(使用)についても処罰されることになりました。
大麻をはじめとする麻薬を施用するためには、麻薬施用者の免許が必要となります(同法第3条)。この免許がなく、大麻を施用した場合、7年以下の拘禁刑に処されます(第27条第1項・第66条の2第1項)。「施用」と規定されていますが、免許なく他人に治療などの名目で使うだけでなく、自分自身で吸ったりする場合も「施用」に該当します。
営利の目的で行った場合は、1年以上10年以下の拘禁刑、または情状によりさらに300万円以下の罰金に処されます(第66条の2第2項)
大麻草の栽培に関する規定の整備
大麻取締法は、大麻草の栽培の規制を中心とする法律に改められ、令和6年12月12日より「大麻草の栽培の規制に関する法律」が施行されました。
大麻草の製品の原料として栽培する場合を第一種大麻草採取栽培者、医薬品の原料として栽培する場合を第二種大麻草採取栽培者としました。
第一種大麻草採取栽培者は栽培地の属する都道府県知事の免許、第二種大麻草採取栽培者は厚生労働大臣の免許を受けなければなりません。その他、大麻草を研究する目的で栽培する者も、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります。
このような免許もなく、大麻草をみだりに栽培した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処されます(大麻草の栽培の規制に関する法律第24条第1項)。営利の目的で行った場合は、1年以上の有期拘禁刑、または情状によりさらに500万円以下の罰金に処されます(第2項)。
医薬品の施用等を可能とするための規定の整備
従前は大麻から製造された医薬品の施用などは禁止されていました。しかし、国際的にも大麻の医療上の有用性が認められ、大麻の医療上の施用が求められていました。
そこで、上記の大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の改正により、大麻の施用などの禁止規定を削除し、大麻を麻薬として、麻薬及び向精神薬取締法上の免許を受けることにより施用が可能になりました。
まとめ
このように、大麻に関連して、大きな法改正が行われました。大麻の乱用については、コカインやMDMA等のジアセチルモルヒネ(ヘロイン)以外の麻薬と同じように処罰されます。
大麻をはじめとする麻薬については、「麻薬及び向精神薬取締法違反」の記事もご覧ください。