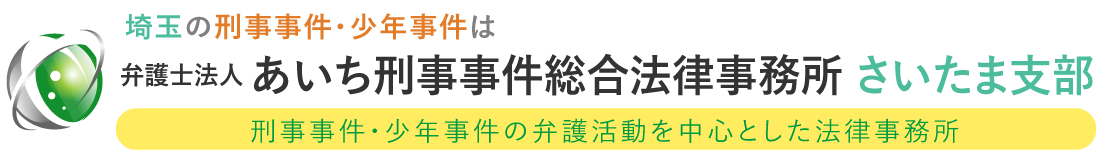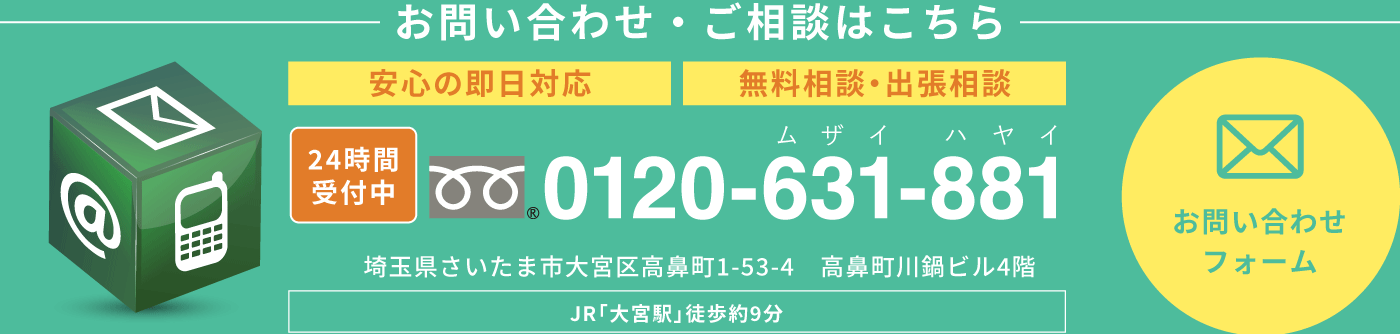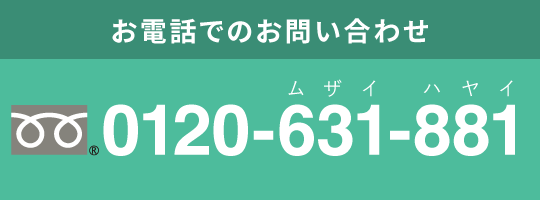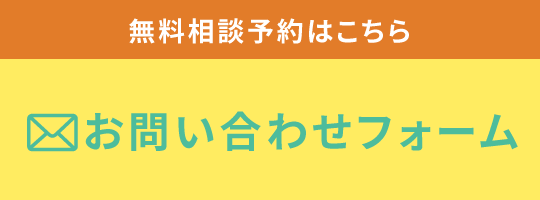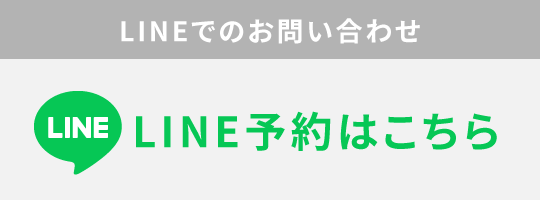・執行猶予判決とは
「執行猶予判決」とは拘禁刑を言い渡されても,一定の期間は刑務所へ入らなくてもよい判決のことです。
執行猶予付きの判決がつけば,有罪判決の場合でも刑の執行が一定期間猶予されます。
ただ,執行猶予付きの判決であっても,有罪判決であることには違いありませんので,残念ながら前科は残ってしまいます。
しかし,通常の生活をすることができる点で大きなメリットがあります。
・執行猶予判決の要件
一般の執行猶予の要件は,
- 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことのない者,又は,その執行を受け終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことのない者が
- 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは
- 情状によって裁判確定の日から1年以上5年以下の期間内,その執行を猶予するもの
と規定されています。
また,再度の執行猶予として,前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予された者が,2年以下の拘禁刑の言渡しを受け,上場が特に酌量すべき場合にも,その刑を猶予することが認められています。
なお,一般の執行猶予は裁量的に,再度の執行猶予では必要的に保護観察に付せられます。この再度の執行猶予の保護観察の期間内(後述の保護観察の仮の解除がされた場合を除きます)に更に罪を犯したときは執行猶予は認められません。
・保護観察とは
保護観察中に,定められた事柄(遵守事項)を遵守するよう対象者を指導・監督し、あるいは、本来対象者自身が自ら更生のために努力しなければならない、という自助の責任を認めて補導・援護を行うことで、対象者の改善・更生を図るという制度です。健全な生活態度を保持しており、保護観察を仮に解除しても改善更生できると判断されれば、期間の途中でも保護観察が仮に解除されることがあります。
・執行猶予付き判決を得るためには
執行猶予付き判決を得るために,まずは犯した犯罪の内容や犯罪の悪質性が重要であることはもちろんですが,被害者がいる犯罪の場合,「示談」が成立していることのインパクトは大きいといえます。
また,社会内で更生するための環境が整っていることを示すために,ご家族に協力していただいたり,本人の更生の意思を具体的に示したりすることが執行猶予を勝ち取るうえで大切なことです。
・執行猶予が取消される場合
執行猶予がついて社会復帰したとしても,新たに罪を犯したり遵守事項を破ったりすれば執行猶予が取消されたり,あるいは取消となる可能性があります。
つまり,執行猶予判決を得て社会に復帰した後は,健全な生活が要求されます。
健全な生活が要求されるとはいうものの,基本的には以前と変わらない社会生活を送ることが可能です。
捜査機関に一日中見張られているというようなこともありません。
ただし,以下に示すように,執行猶予が取り消される場合があります。
二度と罪を侵さないようにするのはもちろんのこと,交通事故を起こしてしまった場合にも執行猶予が取り消される可能性があります。
(1)必ず執行猶予が取り消される場合
- 執行猶予期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の実刑の言渡しがあったとき
- 執行猶予言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の実刑の言渡しがあったとき
- 執行猶予言渡し前に,他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき
(ただし,発覚した罪についての刑の執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者を除く。)
(2)執行猶予が取り消される可能性がある場合
- 執行猶予期間内に罰金に処さられたとき
- 保護観察付きの執行猶予期間中に保護観察に付された者が,その間守るべき事項を守らず,その情状が重いとき(保護観察が仮に解除されている場合を除きます)
- 執行猶予言い渡し前に,他の罪について拘禁刑に処せられ,その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき
・執行猶予の効果
刑の全部の執行猶予の言渡しをされれば、刑務所に行かずに済みます。
また、執行猶予を取消されることなく猶予期間を経過すれば、刑の言渡しは効力を失います。
・執行猶予に関する法改正
令和7年6月1日の改正刑法の施行により、執行猶予に関してもいくつか変更されました。
(1)再度の執行猶予の要件の緩和
改正前は1年以下の懲役又は禁錮(現在は拘禁刑に統一されました)に限り再度の執行猶予が認められていましたが、改正後は、上記の通り、2年以下の拘禁刑であれば、再度の執行猶予が認められます。
また、改正前は裁量的であれ必要的であれ、保護観察が付いていた場合再度の執行猶予は認められませんでした。改正後は、再度の執行猶予において必要的に保護観察が付された場合に限り、再度の執行猶予が認められないことになりました。なお、この保護観察も仮の解除がされていれば、これが取消されるまでは保護観察に付されなかったものとみなされるので、再度の執行猶予は認められます。
(2)執行猶予の効果の継続
執行猶予を取消されることなく猶予期間を経過すれば、刑の言渡しは効力を失いますが、改正前は、執行猶予期間中に罪を犯した場合でも、判決が確定するまでに猶予期間が経過すれば刑の言渡しは効力を失い、執行猶予は取消されることがなく、さらなる執行猶予も可能でした。
改正後は、刑の全部の執行猶予の期間中にさらに犯した罪について公訴の提起がされているときは、刑の言渡しは、執行猶予を取消されること(拘禁刑以上の刑に処されて刑の全部の執行猶予の言渡しがないため必ず取消される場合と、罰金刑に処せられて裁判所の判断により取消される場合があります)がなくなるまでは、期間が経過しても効力は続くことになりました。裁判が長引いたり、控訴や上告をして期間が経過しても、猶予期間中に犯罪を起こしていたのであれば、再度の執行猶予が認められなかったり執行猶予を取消されることがあります。
執行猶予判決を勝ち取りたい方,実刑になるかもしれないと悩んでおられる方は,執行猶予判決の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。
さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,執行猶予判決の見通し及び執行猶予獲得に向けた対応方法等をアドバイスいたします。
刑事事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。
・一部執行猶予とは
(刑の一部の執行猶予)
第27条の2
1 次に掲げる者が3年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
・一部執行猶予制度とは
一部執行猶予付きの判決内容としては,「被告人を3年の拘禁刑に処する。その刑の一部である1年の執行を3年間猶予する。」するというようなものになります。
簡単に言えば,この場合,2年間は刑務所で受刑した後釈放され,残り1年間については,3年のうちに執行猶予が取り消されることがなければ受刑する必要がなくなるという規定になっています。
また、一部執行猶予の猶予期間中は、保護観察に付することができます。この保護観察は行政官庁の処分により仮に解除することができます。
なお、令和7年6月1日施行の刑法改正により、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでにさらに犯した罪について公訴が提起されているときは、刑の一部の執行猶予の取消がされることがなくなるまで、元々の猶予期間が経過しても効力は残り続けますので、猶予期間満了直前に罪を犯してしまうと、その事件の判決が元々の期間満了後に下されたとしても、執行猶予が取消されることがあります。
・薬物犯罪の場合
薬物犯罪に関しては,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」によって,刑法の特則が定められています。
すなわち,薬物犯罪の場合は刑法に規定されている前科に関する要件は適用されません。
また,薬物犯罪に関して一部執行猶予が適用される場合には,必ず保護観察に付されることとなっています。
一部執行猶予について不安や疑問がある方、一部執行猶予付き判決を希望される方は、執行猶予及び一部執行猶予実績の豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご相談ください。
さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う経験豊富な弁護士が,直接、執行猶予及び一部執行猶予付き判決の見通しについて説明したうえで対応方法をアドバイスいたします。
刑事事件の当事者の方が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。